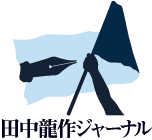セリ落としたマグロを自分の店に持ち帰る仲卸業者。仲卸街区はセリ場に隣接する。100m以上も離れた豊洲に行けばこの光景はなくなるだろう。=11日午前6時、築地場内 撮影:筆者=
築地市場を1年半近くに渡って撮影したドキュメンタリー映画、「築地ワンダーランド」が今週末から全国上映される(制作・配給:松竹)。先行上映に足を運んだ。
目もくらむような多種多様な魚、人、交わされる会話の中から「築地市場とは何か」が浮かび上がってくる仕掛けだ。
消えゆく前世紀の遺物としての築地ではなく、あくまで今の市場としての姿を活写している。ここから、豊洲移転の問題点も分かってくる。
築地市場はあたかも有機体のようだ。大卸(魚を産地から集める業者)、仲卸、買出し人・・・人が無意識のうちに手足を動かしているのと同じように、それぞれが自分の仕事を全うすることで全体が回っている。
食の権威、名人と言われる人々が口を開く。料理評論家の山本益博氏は「世界一ではない。世界唯一、オンリーワン。あれに匹敵するものは世界に無い」と断言する。
すきやばし次郎は「あそこが無かったら商売にならない」と全幅の信頼を置く。
実は、オンリーワンなのは物流や売上高だけの話ではない。「築地ワンダーランド」では魚の評価・分化機能を仕事とする、仲卸と呼ばれる仲買人にスポットを当てる。
評価とは値付け、分化とは、必要とされる客(魚屋や料理店)のニーズにあった商品を渡すこと。仲買人の存在こそが世界の他の市場と違う、築地をオンリーワンたらしめているのだ。

長さ2mはあるマグロ包丁。豊洲の店舗は狭く仕切られているため、マグロ包丁を使うのにも支障をきたす。=11日午前6時、築地場内 撮影:筆者=
仲卸は魚種別に細かく分類されている。マグロ専門の大物業者、鮮魚、塩干・・・。彼らはセリでニオイや色、手触りなど五感を研ぎ澄ませながら魚を選ぶ。
仕入れてきた何十種類、何百匹という魚の中から、季節や買い手の要望にぴったりと合った個体を選り分けて渡す。客のニーズを知るために仲卸たちは買い出し人が経営するレストランに足を運び、どんな料理に使うのかまで見極める。
新鮮さを保つ下処理、切り分け方などは、職人芸であるとともに、科学的根拠も踏まえたものだ。
仲卸たちのプロ意識は半端ではない。曰く、「漁師さんが命がけで獲ってる魚を、喜んでいるお客さんに渡す」、「旬というのは一年で一番おいしい10日間」、「市場ってのは、土俵だと思ってる」、「俺はまぐろ屋だ、ビジネスマンではない」。
身銭を切って勝負するセリで培った意地と、自分の専門に対するプライドがある。彼ら「目利き」がいいものを見極めたというお墨付きが「築地直送」というブランドになる。
アナゴ専門の仲卸は言う。「自分、もうアナゴしか知らない。この仕事でなきゃ生きていけない」。
こういう仲卸が商品に的確な情報を付加して売ることで初めて、寿司職人は“仕事”をすることができるのだ。

「市場カゴ」を手にした料理人や小売り業者が直接、買い出しに来る。彼らは「豊洲に移ったら行かないよ」と口々に言う。=11日午前6時、築地場内 撮影:筆者=
豊洲と築地では何が違うのか。築地ではセリ場と仲卸が渾然一体になっている。いっぽう、豊洲では広い道路で分断され、建物自体も閉じている。 豊洲がこんな建物になったのはTPPで義務化されるであろう、HACCP(ハサップ)や、コールドチェーンを前提としているためだ。
「築地ワンダーランド」では仕切りのない店舗で、ちょいと隣の若い衆と話を交わし、品物を融通し合い・・・という日常が描かれる。
仕入れのアテが外れた時、同業者から買うことを「仲間買い」という。10代で市場に入り、70歳を越すまで現役が珍しくない築地では、お互いが商売敵である以上に仲間なのだ。
その築地を更地にし、オリンピックの駐車場にするのだとか言っているらしい。とんでもない話だ。
築地市場の中では神の見えざる手が働いていて、“目の前の売り買い”と“日本文化の下支え”がベストバランスで成り立っているのに、その「場」を壊そうというのだ。
築地を「ワンダーランド」たらしめているタテ、横のつながり、産地へのリスペクト、客との信頼関係――それらのコミュニケーションを断つような設計がされている豊洲では、仲卸達は今までのように動くことができない。
豊洲移転問題が「汚染度の軽重」や「建物の強度」だけの問題と思っている人は、東京都が結論を出す前に「築地ワンダーランド」を観るか、現地へ足を運んでほしい。
築地を壊すことは、日本文化を自ら壊すに等しいということが分かるだろう。
~終わり~
◇
【記者志望の学生求む】
『田中龍作ジャーナル』では取材助手を募集しています。時給1,500円以上・交通費支給。就職実績:大手新聞社・大手通信社・出版社。
勤務時間は柔軟に対応します。危険地帯への同行はありません。詳しくは…tanakaryusaku@gmail.com