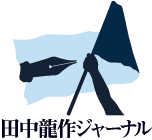SLAPP裁判の事実上の勝訴を祝う会が17日、開かれた。右が田中稔氏。隣は妻の惠子さん。=千代田区 写真:筆者=
大企業や政府などが資力に飽かせて個人を狙い撃つ恫喝訴訟(SLAPP=Strategic Lawsuit Against Public Participation)。日々の生活に汲々としているフリージャーナリストを黙らせるにはもってこいだ。
組織に所属していても記者個人に絞ってSLAPPを掛けてくるケースもある。田中稔氏がそうだった。田中氏は『社会新報』の記者だが、一個人として週刊金曜日に寄稿した記事をめぐり名誉棄損で訴えられ、6,700万円もの損害賠償を請求されたのである。一介のサラリーマン記者が背負える金額ではない。
田中氏がSLAPPを掛けられた記事とは―
週刊金曜日(2011年12月16日発売)に掲載された『最後の大物フィクサー』と題する記事で、警備会社社長を中心にした原発の利権構図をリポートした。警備会社社長側は「フィクサー」などとする表現が名誉棄損にあたるとして田中氏だけを告訴した。週刊金曜日を対象にはしなかった。
かつての名誉棄損は媒体とライターの両方を訴えるのが普通だった。経済力のないライターだけを狙い撃ちするのがSLAPPの特徴だ。一個人として執筆したため、田中氏が所属する『社会新報』はバックアップしてくれなかった。
訴えられた田中氏の苦闘が始まった。6,700万円という途轍もない金額が肩に重くのしかかった。法廷闘争に注がなければならない労力も生活を圧迫した。
土地・建物・法人登記や企業調査資料など証拠提出書類は144点。準備書面など裁判所に提出した書類は1,200ページ以上にのぼった。
「証言集めや裏づけ作業などに追われ心身ともに疲れ果てた」「仕事にも身が入らず職場の同僚に迷惑をかけた」「家族にも心配をかけた」と田中氏。
記事中の「塀の上を歩き続けた」との表現は、名誉棄損の裁判上きわめて厳しいと弁護士に指摘された。「数百万円を払うことも覚悟した」。田中氏は苦悶の表情を浮かべながら話した。
だが背水の陣でのぞんだ田中氏の地道な努力は報われる。フィクサーとされる警備会社社長側が裁判を取り下げたのである。8月半ばに予定されていた本人尋問の直前だった。原告の社長と被告の田中氏が初めて法廷に立つ。決定的な事実が飛び出すかもしれない、裁判のクライマックスだった。
原告は知られたくないことがあったのか。今となっては知る由もないが、本人が法廷に立ち証言することもなく、裁判を取り下げたのである。

昨年8月、開かれた田中稔氏を励ます会。「国境なき記者団」東京代表の瀬川牧子氏(右)は原発SLAPPを国際世論に訴えた。=阿佐ヶ谷 写真:筆者=
~仕掛けた方が恥をかく/法整備も必要~
フリージャーナリストの烏賀陽弘道(うがや・ひろみち)氏は2006年、ジャニーズのヒットチャートについて雑誌に載せられたコメントをめぐって音楽情報会社からSLAPPをかけられた。音楽情報会社は5,000万円の損害賠償を烏賀陽氏にだけ求めた。
裁判は2審で和解したが、1審は敗訴。東京地裁は烏賀陽氏に「音楽情報会社に100万円を支払うよう命じた」のである。
烏賀陽氏は33か月に及ぶ裁判で約1,000万円を損失した、という。弁護士費用と失った仕事を合わせた金額だ。田中氏同様、訴訟に多大な労力を費やした。
田中氏の事実上の勝訴について烏賀陽氏は「7年間でこれほど状況が変わるものか」と喜んだ。米国のSLAPP事情に詳しい烏賀陽氏によれば、カリフォルニア州にはSLAPPを禁じる法律があり、米国の80%の州ではSLAPPと断定された場合、弁護士費用は原告(SLAPPを起こした側)が負担しなければならない。
消費税やTPPに関する報道が象徴しているように、マスメディアは政・財・官におもねりがちだ。フリーランスが権力の監視役を果たそうにもSLAPPによる口封じがある。
「日本でもSLAPPを抑止する、SLAPP被害を防止する法律が必要」と烏賀陽氏は指摘する。日本で法整備を期待することは難しいが、田中氏や烏賀陽氏の裁判例が示すようにSLAPPは掛けた方が社会的なイメージを損ねる。
とは言えSLAPPの前にフリー記者は無防備だ。彼らを守る枠組みはないものか。