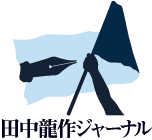侵攻してきた国(イスラエル)の軍隊と地元の武装勢力が激突する。紛争地帯に「治安」という文字はない。誘拐されて当たり前の環境である。ベイルートから南へ107㎞。=25日、ベルトジュバイル村 撮影:田中龍作=
1985年にはAP通信のテリー・アンダーソン記者が拘束され、7年近くもヒズボッラーの管理下に置かれた。
ヒズボッラーの支配地域に入らないことにはレバノン戦争の実相はつかめない。だが拘束のリスクを伴う。
田中のようなフリーランスや一流の海外メディアは、日本のマスコミのように安全な場所で記事を書いて済ませるわけにはいかない。

目の前のイスラエル軍基地を監視するレバノン軍兵士。軍がいれば少なくとも誘拐はない。ベイルートから南へ93㎞。=25日、イスラエルとの国境地帯 撮影:田中龍作=
リスクを避けるには手練れのドライバーや手練れのフィクサー(通訳兼コーディネーター)と共に危険地帯に入り、彼らの指示に従うことだ。
目を瞠る光景に出くわしても彼らは「写真を撮るな」「ここでは車から降りるな」と怒鳴るようにして言う。誰が見ているか分からないからだ。ヒズボッラーの戦闘員に突き出されたらお終いである。
危険地帯の取材では取材車の車内から撮影した写真が大半を占めることになる。
ドライバーやフィクサーが経験則に基づいてOKだと判断すれば「車を降りて撮影してもいいけど、クイックリーだぞ」となる。

撤退したイスラエル軍のトーチカ(内側)とヒズボッラーのロケット砲。ベイルートから南へ107㎞。=25日、ベルトジュバイル村 撮影:田中龍作=
国を跨いだ場合、ドライバーやフィクサーが交代することが多い。例えばエジプトからリビアに入ったとする。
エジプトのフィクサーは、リビアの勝手が分からない。そこでリビアのフィクサーに田中を委ねる。リビアのフィクサーをLさんとしよう。
Lさんとは順調に取材が進み、カダフィ独裁政権の倒壊を見届けることができた。だがLさんは自身の都合でフィクサーの継続が不可能になった。
信頼できるフィクサーは2人目までだ。3人目からは「友達の友達は友達」でなくなるのだ。田中はハタと困った。リビアの砂漠で一人ぼっちになってしまったのである。
Lさんが「俺の息子を紹介する」と薦めてくれたが、断った。息子は好青年かもしれないが、不良かもしれないのだ。
戦乱の地で簡単にフィクサーは見つからない。かといって知りもしない人間にこの身を委ねれば、売り飛ばされたりする。
田中は投宿先のホテルに頼んでタクシーを仕立てた。そしてエジプト国境まで逃げた。ひと通りの取材を終えていたこともあるが。
用心に用心を重ねても決して安心はできない。拉致拘束されなくても銃撃に遭うこともある。イスラエル軍のドローンから対人ミサイルを見舞われることもある。
~終わり~
◇
【読者の皆様】
田中龍作ジャーナルは読者のお力により維持されています。今回も借金に借金を重ねての取材となりました。