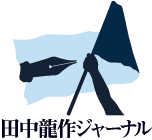「この世界の片隅に」は満員御礼が相次ぐ。休日は空席を見つけるのが難しい。=28日、渋谷 撮影:筆者=
第二次世界大戦の戦況が悪化の一途をたどるようになった昭和19年(1944年)、主人公の北條(旧姓・浦野)すず は、広島から呉に嫁ぐ。数えで19歳の春だった。
呉の鎮守府(海軍管区統括機関)で軍法会議録事(書記官)を務める夫の北條周作は、幼い頃、広島の橋の上で出会ったすずを見初め、苦心惨憺の末、彼女を探し出したのだった。それゆえ妻への愛情は人一倍深い。
食料が配給制となり、食卓が寂しくなってもすずは工夫を重ねて家族の空腹を満たした。着物はモンペに仕立て直した。当時としては、普通の奥さんだったのである。
昭和19年も押し詰まった頃、すずの幼なじみの杉原哲が訪ねてくる。水兵として乗り込んでいた巡洋艦「青葉」がルソン島西方で破損したため、呉に帰投したのだった。
「死に遅れるゆうんは、やりきれんもんですのう」。杉原はうめく。
周作は杉原を「離れ」に泊めるが、すず にカイロを持って行かせる。寛大だ。
杉原と同衾した すず は「ず~っとこうなる日を待ってたけど、あの人(夫・周作)のことがホンマに好きなんや」と激しく嗚咽する。
翌朝、杉原は「どこでワシは人間の当たり前を見失ったんかのお? お前だけは最後までこの世界で普通におってくれ」と言い残して去って行った。杉原はそのまま帰らぬ人となった。
昭和20年(1945年)になると海軍鎮守府と兵工廠(工場)のある呉は、連日空襲に見舞われるようになる。
焼夷弾が北條家の屋根に落ちたが、大火には至らずに済んだ。

精緻な時代考証により当時の呉の街並みが、そっくり再現されているという。戦艦大和は呉の海軍工廠で建造された。
すずは姪の はるみ を連れて海軍病院に義父を見舞った帰りに空襲に遭う。時限式の爆弾が炸裂。はるみは命を奪われ、すずは右手を失った。
「(義父は)家の火が大きくならんで良かった、と言う。医者は腕の治りが早くてよかった、と言う。皆、良かったと言うが、どこが良かったのか、私には分からんかった」。
異常が当たり前になって行く時代の怖さだ。すずの自問自答はそれを指摘する。
戦争が終わると すず は真っ先に原爆が投下された故郷の広島に向かった。
後を追って来た周作は橋の上で すず を見つける。二人が初めて出会った場所だ。
すずは言う。「この世界の片隅でウチを見つけてくれて有難う」と。限りなく優しい夫への感謝だ。
原爆で母親を失い腹を空かせた女の子を、周作とすずは呉に連れて帰った。呉の街に明かりが灯る。戦前と同じ景色が戻ってきたのである。当たり前の尊さが身にしみる ― これがラストシーンだ。
極限状況にあっても人間性を失わない人たちがいる。イスラエル軍の侵攻(2014年)で家を失ったガザの夫婦は、自分たちも ひもじい にもかかわらず、田中にパンをすすめてくれた。
「この世界の片隅に」は、静かで哀しくそして強烈なメッセージが託された反戦映画である。
~終わり~