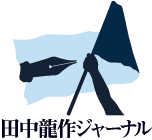【カブール発】 治安の悪化が伝えられるアフガニスタンを5年ぶりに訪れた。米国が錦の御旗のごとく掲げる「テロとの戦い」の下で、人々の暮らしはどうなっているのかを取材するためだ。
前回(2002年)の取材では、パキスタンの北都ペシャワールから、アフガニスタンとの国境に跨る部族地帯を通り陸路でカブールに入った。今、このルートを使うには、武装したコンボイを組まなければ、安全は保証されない。このため今回は空路でのカブール入りを余儀なくされた。
国連をはじめ各国が復興支援のため莫大な資金を投下する一方で、反政府勢力タリバーンの攻勢は衰える気配がない。各地の軍閥も時に活発な動きを見せている。
米国に後押しされたアフガニスタン政府がコントロールできている州は、タリバーンと各軍閥が実効支配する州よりも圧倒的に少ない。「カルザイ大統領はカブール市長」と揶揄されるゆえんだ。
前回訪れたのは、「ロヤジルガ(民族大会議)」が開かれ、新憲法が採択された頃だった。新生アフガニスタンの夜明とも言えた。
長きにわたる内戦に一応の終止符が打たれ、首都カブールは活気に満ちていた。治安も良く夜中に外を出歩くこともできた。民家に宿泊していた筆者は、メールを出すのに毎晩のようにホテルに出かけていた。
ところが今では、外国人の一人歩きは日中でも危ないと言われる。誘拐や爆弾テロに遭う危険性があるからだ。夜中に出歩くのは自殺行為に等しい。
砂ぼこりを被って白くくすむカブールの街は、5年前とほとんど全く変わっていなかった。紛争各派と米軍が撃ち込んだロケット弾で破壊されたまままの家屋は、今なお数えきれないほどある。当り前の風景として街に溶け込んでいるのが痛々しい。戦乱に明け暮れてきた国の宿命だろう。
街角のあちこちに物乞いがいるのも、当時のままだ。車を停めれば子供がやって来て現金を渡すまで車から離れない。渡しても少額紙幣だと泣き声がさらに大きくなる。物乞いの子供も相当に「支援ずれ」しているようだ。

カブール進攻をうかがうタリバーン
カブール西郊外のゴルバッグ村。山裾の同村はアフガニスタン戦争(2001年~)の際、タリバーンの基地があったことから米軍の空爆を受けた。瓦礫となった家屋の復旧作業が今も続いている。
NATO軍は山岳地帯に潜みカブール侵攻の機会を伺うタリバーンの掃討作戦を続けている。ゴルバッグ村ではフランス軍と米軍の装甲車が山岳方面に向けてせわしなく進んでいた。2~3分もしないうちに攻撃ヘリ・アパッチが同じ方向に飛んでいった。
筆者の取材車も後を追ったが、山岳地帯に続く道路の入り口で国軍兵士に止められれた。「ここから奥に行ってはならない」。
村人に聞いた。「タリバーンは(我々に)協力的だったけどNATOは問題を起こすだけだ。みんなNATOに怒っている。(NATOが展開するようになって)山あいの診療所に行くことができなくなった」などと口々に語った。
答えてくれた村人たちはタリバーンと同じパシュトゥー民族なので、差し引きして聞く必要がある。だがはっきりしていることがある。タリバーンの足音が首都カブール近くまで迫っているということだ。NATO軍の展開が村人の安穏な生活を妨げているのも事実だ。
カブールの街が一向に復興しない理由を、あるビジネスマンが話してくれた。「いつまた戦闘が始まるかわからないカブールに、誰も本気で投資などしない」。

ゴルバッグ村を訪ねた翌日、爆弾テロ犯5人がカブールに侵入したとの情報があり、街は厳戒態勢に包まれた。市民の数より兵士の方が多いのではないかと錯覚せるほど、街は武装した兵士であふれた。
カブールでは何事もなかったが、南に隣接するパクティア州では爆弾テロがあり多数のISAF兵士と市民が死傷した。