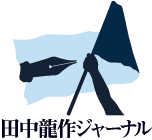学校を卒業し新聞社、テレビ局、通信社に入ると最初に担当させられるのは警察取材だ。業界用語で「サツ回り」と呼ぶ。事件が起きると広報課(報道課)が容疑者の住所、職業、年齢はもとより逮捕容疑までを列記した発表用紙を出す。
発表用紙は横書きだが、そのまま縦に書き写せば曲がりなりにも原稿になる。普通、自分で取材し直して肉付けするが、ベースはこの発表用紙だ。実に便利な代物である。
書かれている内容はすべて警察側から出たものだ。容疑事実も供述も、すべて警察にとって都合のいいストーリーで描かれている。「被疑者は容疑を認める供述を始めている」などというフレーズもちょくちょく登場する。
“すべて警察側の発表でいいのだろうか?容疑者の言い分は取材しなくていいのだろうか?”最初は誰でも疑問を持つはずだ。筆者は違和感を覚えて仕方がなかった。後ろめたい思いすらした。
ところが半年も過ぎればこの感覚はなくなる。警察幹部からどれだけ捜査情報を聞き出してくるかが社内での評価対象となる。捜査情報というのはリークである。
メディアの記者たちは一年生の時から当局の発表やリーク漬けが当たり前の環境のなかで育っていくのだ。
大阪、東京地検特捜部が手がける事件は記事の扱いも大きくなる。記者にとってリークは有難い情報源となる。検察はリークを餌に記者を手なづけることとなる。
大阪地検特捜部の主任検事が証拠隠滅で逮捕された事件が改めて示しているように、検察は自らが仕立てたストーリーに沿った供述調書を公判に提出する。そして有罪を取りに行く。
「被告は『●●先生のためにやった』と涙ながらに供述し始めた」などとするリークがそのまま記事となり、読者・視聴者の頭に摺り込まれていく。被告の社会的生命は半ば奪われるようなものである。ここが検察の狙い目だ。
検事は「これ以上マスコミに書かれたくなかったら容疑を認めたらどうだい?外に出られるし執行猶予だってつくんだから」などと脅してスカしあげる。これで多くの被告は供述調書にサインするのである。『記者クラブメディアは冤罪に手を貸している』とするのはこのことだ。
メディアが冤罪に手を貸すことを防ぐためには検察記者会見のオープン化しかない。フリーやネット記者を入れビデオ撮影を認めれば、どこまでが発表でどこからがリークなのかが分別できるはずだ。
フリーやネット記者がリークを受けて書いたりすれば、たちまち読者を失う。だからリークでは書かない。先ず記者会見の可視化をしようではないか。取調べの可視化は法改正などのため多少の時間を要するが、記者会見の可視化(=オープン化)は明日からでもできる。
*海外在住の皆様も、日本の皆様も、ご自宅から*
オンライン決済サービス Square上で、クレジットカードによる『田中龍作ジャーナル』へのご寄付が可能となっております。
お手元のPCやスマホから手軽に振込めます。面倒な登録は一切ありません。深夜でも可能です。
[田中龍作の取材活動支援基金]*ご自宅から何時でも、24時間 御支援頂けます*
Twitter