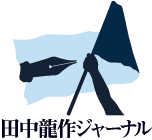子供が消えた幼稚園。事故前、住民のほぼ全員に防毒マスクが配布されていたが、一度も使われることはなかった。=16日、プリピャチ。写真:田中撮影=
チェルノブイリ原発から西へ車を10分も走らせると人ひとり住んでいないゴーストタウンが現れる。原発労働者の街だったプリピャチだ。ホテルやアパートの窓ガラスは粉々に割られ、家具も見当たらない。物盗りの仕業だろうか。あれから26年が経過し、人が暮らしていた匂いは全くない。絵に描いたような廃墟だ。
1986年4月26日、チェルノブイリ原子力発電所がメルトダウンを起こすと、住民4万5千人がプリピャチから脱出した。うち子供は1万7千人。子供たちはソ連との共有地域とウクライナ各地にある保養所に避難した。
当時シベリアの病院に勤務していたステパノバ・イエゲニア医師(現在、ウクライナ医療放射線研究所・小児科部長)は、ウクライナに移り住み、約5,000人の被曝者を診療した。
ステパノバ医師によれば、ソ連は子供たちの体内被曝を避けるために幼稚園や学校に放射能で汚染されていない食材を送った。
甲状腺、胃腸、血液、ガンの専門医がチームを組んで、子供たちのいる各地の保養所を回った。バスに甲状腺を検査する超音波測定器を積んで。
子供の健康調査が遅々として進んでいない福島県とは行政の姿勢が180度違う。体内被曝についても日本政府は「食べて福島を応援しよう」だ。最近やっと沈静化したが、学校は給食食材の放射能汚染について配慮を欠いていた。

かつての豪華ホテルの最上階から街を望む。原発労働者用のアパートの向こうにチェルノブイリ原発4号機が見える。=16日、プリピャチ。写真:田中撮影
ひとっこ一人いないプリピャチのあちこちで線量計が1・5μSv/h前後を示した。福島市内の線量が高い地区と同じレベルだ。福島市内にはなお25万人以上が暮らす。経済的な理由から転校できない子供たちは数えきれない。6月には子供10人の尿からセシウムが検出された。
共産党独裁のソ連でさえ子供たちを被曝から救うため、上述したようなあらゆる手段を尽くした。日本はどうだろうか。手をこまねいてばかりの政府に市民の間から「福島の子供たちを一刻も早く避難させよ」との声が澎湃としてあがる。民主主義を標ぼうしながら、子供をおろそかにする国に将来はないのである。
《文・田中龍作 / 諏訪都》