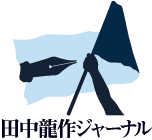小橋川さんが持つ杖は、「墜落した米軍機のジェット燃料で燃えた宮森小学校校舎の木片と融けた金属」を模している。憎しみのオブジェだ。=キャンプ・フォスターのゲート上で。写真:田中撮影=
16日午後9時、上原さんはドクターストップがかかった。血圧が高くなっており、「これ以上続けるとしばらく入院しなければならなくなりますよ」と医師が言い、上原さんはそれを受け容れた。85歳の体に沖縄の蒸し暑さは酷だった。
小橋川さん(69歳)は、医師が勧める経口補水液を飲みながらハンストを続けている。「(ハンストは)思った以上に疲れる」とこぼしながらも、肌には張りがあり目もランランと輝いている。「命の続く限り(ハンストを)続ける」と気力も充実している。
小橋川さんはキャンプ・フォスターのゲートから断わりもなくグングンと基地の中に進んで行った。「入って来ないで下さい」と警備員から制止されてやっと立ち止まった。
「警備員もウチナンチュ(沖縄の人)さ」。敵を作らない小橋川さんらしい言葉だ。小橋川さんの柔和な人柄に惹かれる人は少なくない。サポーターとしてハンストを側面から支える。
だが小橋川さんの奥さんはハンストにいささか懐疑的だ。「アンタばかじゃないの。私ら家族が迷惑しているんだよ。オスプレイが落ちたら死ねばいいさ。諦めれば怖くないよ…」。
小橋川さんは言い返した。「命はつながっているんだよ。孫も生まれたばかりだよ」。孫は嘉手納基地の飛行ルートのすぐ傍に住む。

オスプレイ配備に反対するウチナンチュたちが、ハンスト支援に次々と訪れた。=ゲート傍。写真:田中撮影=
ハンストの輪を広げるために小橋川さんは懸命だ。「無期限でなくてもいい。1日だけでも、半日でも、2時間でもいい」。携帯電話や口コミで声をかけまくる。
反応はいい。「日曜日●●さん、月曜日■■さん……」小橋川さんのノートには、ハンスト参加者の名前がびっしりと書かれていた。
小橋川さんは友人に「軽トラック一杯分の畳を持って来てくれ」と注文した。畳は屈伸運動をしたり、体を横たえたりすることができる。ハンストを長続きさせるには持ってこいだ。「時限ハンスト」の支援者が数多く来ても対応できるようにするためである。
「オスプレイが来なくなった時がハンストの終点」。小橋川さんは目を据えて言った。万が一、小橋川さんにドクターストップがかかっても、ハンストの精神は支援者たちに受け継がれる。半世紀以上に渡る米軍の占領支配に対する息の長い戦いとなる。
◇
『田中龍作ジャーナル』は読者のご支援により維持されています。