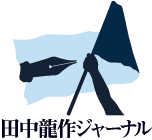7~8年前、実際にあった話だ。3日も一緒に仕事をすれば化けの皮がはがれるインチキジャーナリストAがいた。打ち合わせの段階で対談相手から聞き出した情報を、まるで自分が集めてきたかのように話すので、相手はよく怒っていた。
実力はからきしないが、一流国立大学出身のAは箔をつける狙いもあり単行本を某出版社から出した。
ところがその単行本はルポライターBの作品を剽窃していたことが、初版を出して間もなく暴露された。「て・に・を・は」まで一緒というのだから丸写しもいいところだ。世間をなめているとしか言いようがない。
筆者はAをよく知っていたので、驚きもしなかった。一流の部類に入る出版社の編集者は、Aのインチキ加減をなぜ見抜けなかったのだろうか?担当編集者に電話して聞いた。
「Aは知識もないし、まして自分で取材なんてできるタマじゃない。話していて分からなかったのですか?」
「そ、それが分からなかったんです。こちらとしては損害賠償を求めることでAと話を進めていまして…」。出版社もAの原稿が盗作であることを認めたのである。
自分の作品をパクられたルポライターのBさんは、Aを著作権侵害で訴えて当然なのだが、そうはしなかった。Bさんの原稿もどこからか無断で引っ張ってきたものらしいのだ。
Bさんがぐらついているので告発する人も出て来ず、Aの著作権侵害は“立件”されずじまいだった。盗作疑惑がウヤムヤに終わるケースが多々あるのは、こうした事情からだ。
Bが盗んできた物をAが盗んだ。Bは自分の窃盗がバレるのが怖いからAを訴えない。だからと言ってAの盗みが帳消しになるわけではないのだが。
スキャンダルを得意とする月刊誌の編集者が、Aに事実関係の確認をするために電話取材を申し入れた。
Aは「弁護士に言いますよ」と強がった。
弁護士も何も、出典を言いさえすれば済む話なのだ。
疑惑の目を向けられている人物が出典を明かすことなく、「弁護士からあなたの所に連絡が行く」「法的措置を取る」などという脅し文句を持ち出してきた時、この人物は盗用に手を染めていると判じてよい。
◇