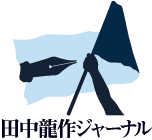小沢一郎が政治資金規正法違反に問われた陸山会事件は、検察とマスコミが捏造した冤罪事件だった。写真は無罪判決が出た瞬間。=2012年、東京地裁前 撮影:田中龍作=
「本部長がウチの検事正に直接電話してきて筋の悪い事件(無理筋)を押し付けてくるんだよ」…田中が若かりし頃回っていた、西日本のある地検で検事からこぼされたことがある。本部長とは県警本部長で、検事正とは地検のトップだ。
県警本部長は警察庁から送り込まれてくるバリバリのキャリア官僚である。警察庁と法務省の力関係からして、検事正といえども県警本部長からの要望は断れないのだ。警察は自らの業績のために、立件したいものは何が何でも立件する。そんな警察の姿勢がよく表れたエピソードだ。
日本の司法において検察が起訴すれば、99%は有罪となる。警察にニラまれたら白も黒となるのだ。
白を黒にするための世論作りに手を貸すのが記者クラブである。容疑者を拘束した時点から、警察は記者クラブを発表漬けにする。記者は被疑者と接触できないので、警察の発表を鵜呑みにするしかない。マスコミは「被疑者真っ黒け」の世論を作りあげてしまうのである。
世論作りをマスコミに勤しませる一方で、警察は自らのスジ書きに沿った自白調書作りに邁進する。被疑者や被告が自白調書に拇印を押すまで勾留し続ける強権的な手法は人質司法と呼ばれる。およそ先進国の司法制度ではない。
そして裁判になると自白調書偏重の判決となる。世論も自白に沿って出来上がっている。

袴田巌さんは無実の罪で45年間も獄舎に閉じ込められていた。「新聞からは『(袴田さんが)犯人で間違いない』と書かれた」。姉のひで子さん(写真)は当時をつらそうに振り返った。=2014年、都内 撮影:取材班=
四国地方のある地裁の判事は朝日新聞を宅配で2部取っていた。1部は購読用。もう1部はスクラップ用だ。裁判官が世論を気にしていることを示す典型例だ。
かりに不自然な判決が出たとしても、記者クラブメディアがそれを指摘することはない。裁判所から至れり尽くせりの便宜を図ってもらっているからだ。「期日簿の閲覧」「判決文の提供」「傍聴席の確保」などである。「記者室の供与」は言うまでもない。
「絶望の裁判所」(講談社)の著者である瀬木比呂志氏は、30年余り判事をつとめ最高裁事務総局に2度にわたって勤務した。日本の司法の裏の裏まで知る人物だ。日本外国特派員協会であった記者会見で瀬木氏に聞いた。「記者クラブと裁判所はお仲間と考えてよいか?」と。
瀬木氏は「そう見ていいでしょうね」と何食わぬ顔で答えた。司法とマスコミの癒着は、彼らの世界では常識なのである。
再審の結果、身の潔白が証明された元被告は「自白は強要されたものだった」と必ず言う。警察、検察が強要した自白をさも事実であるかのように報道する記者クラブは、冤罪製造装置の重要パーツなのである。
~終わり~