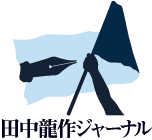インド洋沿岸諸国を襲い23万人が犠牲となった大津波からちょうど4年が経つ。国際援助団体「オックスファム」(本部=ロンドン)は今月一杯で、現地7カ国での支援活動に区切りをつけることになった。
4年間で世界中から2億9400万ドルの寄付が寄せられ、250万人に水、消毒、住宅・学校建設などの支援に役立てた。スポークスマンは「浄財は活かし切った」と胸を張る。

アチェ和平が遺した教訓
大津波で最も多く犠牲者を出したのがインドネシアで16万人、次がスリランカで3万5000人だった。津波発生後間もなく、甚大な被害を受けた2国を筆者は訪れた。インドネシアにはテレビ番組の取材で、スリランカにはNGOに同行して入国した。
震源地のすぐ間近だったインドネシアのアチェは、同国の死者・行方不明者の半数を占めた。天然ガスなどの天然資源が豊かで歴史・文化が違うことから独立を求める武装勢力と中央政府との間で30年間に渡り内戦が続いていた。外国人は全くといってよいほどアチェには入ることができなかった。
だが余りにも大き過ぎる津波被害のためインドネシア中央政府は、国連機関や海外NGOの救援活動に頼らざるを得なかった。天然資源がなかったら見捨てていただろう。海外からの援助がまっとうに行き渡っているかを監視するために、ジャーナリストの入域も許可された。
津波の力は凄まじかった。つい昨日まで漁村だった所は一望荒野となっていた。倒壊した建物は伝染病の蔓延を防ぐため遺体と共に焼いた。木材が焼け焦げた匂いが立ち込めていた。やや生臭かったのは気のせいだったのだろう。海岸から直線距離にして10kmほどある内陸部の街には、船が“流れ着いて”いた。
生き残った人々が生活してゆける状況ではなかった。海岸で貝殻を割っていた主婦は「もし国際社会の援助がなかったら生きてゆけない」と訴えた。
国連諸機関やNGOのテントが数え切れないほど建ち並び、援助物資を満載した大型トラックが砂塵を巻き上げて走っていた。復興に向けた活気がアチェに明るさをもたらしていた。
だが、奥地にまで援助活動に行こうとした海外NGOが射殺される事件がしばし起きていた。中央政府は奥地にこもる武装勢力の仕業であると喧伝した。

筆者も奥地に入った。4輪駆動の取材車は昼は窓を全開にし、夜は室内灯を点けなければならなかった。「私たちは怪しい者ではありません」ということを示すためだ。そうしなければ武装勢力の一味とみなされ、国軍のスナイパーに狙撃される。海外NGOを射殺していたのは国軍だったのだ。
こうした惨劇を経ながらアチェの実情は、国際社会に伝わっていった。津波直後に立ち上がった和平プロセスも前に動き始めた。最大のODA供与国の日本政府もJICAなどを通して「和平を急げ」とネジを巻いた。国際社会の努力は翌年8月の和平調印となって結実した。
「禍転じて福となす」。アチェの人々が受けた甚大な被害の前には軽率な表現かもしれないが、津波を契機に内戦は終結した。
インド洋津波は、大規模な自然災害に遭った場合は国を開き、世界の支援を受け入れることが復興になるという前例を示した。ミャンマー政府は、この教訓をどう受け止めるだろうか。
日本はミャンマーに対しても最大のODA供与国である。ミャンマー政府に対して「国際社会への窓を開けろ」と本腰を入れて圧力をかけるべきだ。