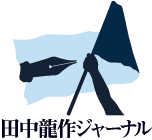下段にはカップヌードルも。値段は99円。=5日、都内 撮影:取材班=
2年前に賞味期限切れになったパンの缶詰が2個100円。1年前に賞味期限が切れているパスタは99円。1月30日までの韓国製ジュースは3個100円。都内某所「訳あり激安」スーパーに置かれた商品の一例だ。
もちろん普通のスーパーのように賞味期限が1年以上ある食品も置いてある。だがここは賞味期限切れがデフォ(定番/前提)だ。客はそれを分かってやってくる。
中にはゴディバのチョコレート小袋が2個298円もあれば、コオロギせんべい49円もある。共通点は「賞味期限切れ」である。
スーパーは駅から3分もかからない場所にある。混雑はないが客足が途切れることはない。ほかにも埼玉県、足立区などに系列店があるが、成城石井や紀伊国屋の立地とは重なっていない。街にはタワマンなどない。

賞味期限切れ食品を買い物かご一杯に買い求める主婦もいた。=15日、都内 撮影:取材班=
激安店の存在は食品流通のなれの果て、とでもいうべきものかもしれない。売れ残った食品は、廃棄するだけでカネがかかる。タダ同然で店に持ちこんで売ってもらえば、激安店側もメーカーや問屋もウィンウィンなのである。
そこへ「エコ」だ、「Mottainai」だ、という美名が加わり、激安店への抵抗感は少なくなった。
お店の言い分はこうだ―
生鮮品など消費期限(いついつまでに食べなければ品質は保証しない。切れたものを売ったら違法)。しかし賞味期限は切れたものを売っても違法ではない。
客からの質問が多いのだろう。レジの所に詳しく説明書きが貼ってあった。
「賞味期限切れの食品を買って何か問題が起きたことがあるか?」とレジの女性に聞いた。
「そういった例はない。自分で(賞味期限切れであることを)納得して買っているので問題はない」。レジの女性はけげんそうな顔をした。

訳あり激安!の看板。店頭に並ぶのは賞味期限切れ食品がほとんどだ。=15日、都内 撮影:取材班=
明治末期、東京に流入した貧困層は軍隊などの厨房から払い下げられた残飯を買って糊口を凌いだ。
ジャーナリスト松原岩五郎は『最暗黒の東京』(1893年出版)の中で、農家がもらうはずの豚のエサや畑の肥やしを、「残飯屋」が貧民たちに量り売りしていた様子を描いている。魚の骨やたくあんの切れ端が入っていれば喜ばれたのである。
「貧民の群れがいかに残飯を喜びしよ、しかして、これを運搬する予がいかに彼らに歓迎されしよ」と。
130年経ち、社会は再び底が抜けつつある。明治の残飯屋は激安食品スーパーに姿を変え、人々の前に現れたとしか思えなかった。
~おわり~
◇
《読者の皆様》
パレスチナ→能登震災→柏崎原発→京都市長選挙と、昨年末から借金が続いております。赤字に次ぐ赤字です。