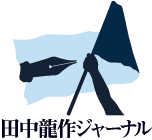海外での取材が首尾よくいくか否かは現地助手の腕しだいだ。世界を揺るがすような特ダネも後にピューリッツァー賞受賞作となるネタの第一報も、大半は彼らがもたらす。
2005年にスリランカを取材した時の助手が忘れられない。少数派民族タミル人の青年で、名はマニカムといった。正確な年齢は聞かなかったが、経歴などから察するに30歳に手が届くか届かないかだろう。
タミル人の取材助手には大変なプレッシャーがかかった。多数派シンハラ人の政府軍と少数派武装勢力タミルタイガー(LTTE)の両方に気を使わなければならないからだ。内戦下にあって軍や武装勢力の機嫌を損ねれば、その晩のうちに消されることも珍しくない。
筆者がタブーに踏み込みたがるため、マニカム青年の前任助手からは逃げられた。前任者は自らと同じ民族であるタミル・タイガー(LTTE)を恐れた。近隣に内通者がいるからだ。「誰が聞いているか分からないからLTTEに絡んだインタビューはしないでくれ」と言って眉を再三しかめた。
マニカム青年も筆者がLTTEの少年兵を撮ろうとすると車のスピードを急加速させたりした。それでも軍が高度警戒区域に指定する場所などには、果敢に取材車を突っ込んでくれたりもした。
監視所の将校に見咎められパスポートを没収されかかったこともあった。危ない橋を渡りながらもマニカム青年は最後まで助手を務めてくれた。
軍に祖先伝来の土地を追われた農民や、浜辺からわずか1キロしか沖に出ることができない漁師の話を聞けたのもマニカム青年のおかげだ。
取材日程を終え現地を発つ朝、空港に向かう筆者をマニカム青年がバス停まで送ってくれた。軍事空港であるため指定されたバスでしか入れないのだ。バスを待つ間の会話は辛いものだった――
「俺を日本に連れて行ってくれよ」。
「それは難しいけど、今度スリランカに来たら、またマニカムに頼むよ」。
「どうせ俺のことなんて忘れるんだろ」。
25年間も続いた政府軍とLTTEの内戦は昨年5月終結したが、最終局面でタミルの人々は「人間の楯」となった。雨あられと降り注ぐ砲弾をかいくぐった人々は内戦終結後、劣悪な環境の難民キャンプに収容された。
国境なき医師団の日本人医師によれば「キャンプの衛生状態はひどく、疾病者は医師の治療を満足に受けることができない」。相当な数のタミル人が命を落としているであろうことは容易に察しがついた。
マニカム青年の無事をひたすら祈るばかりだ。取材助手を依頼する日が再び来ることを願いつつ。